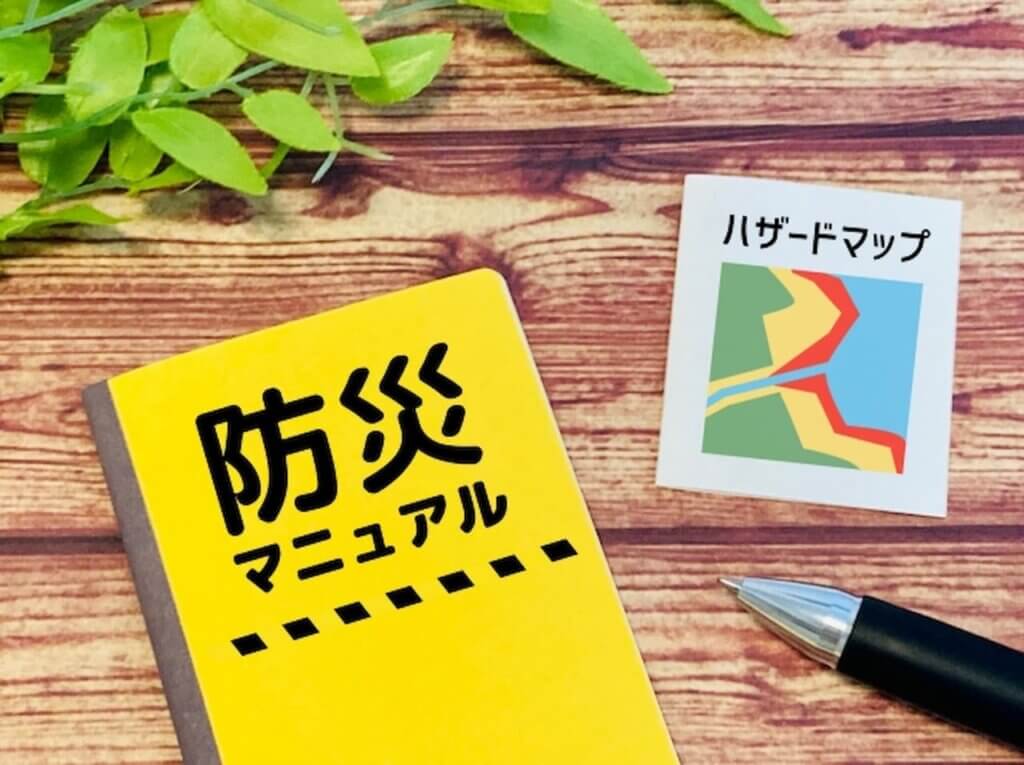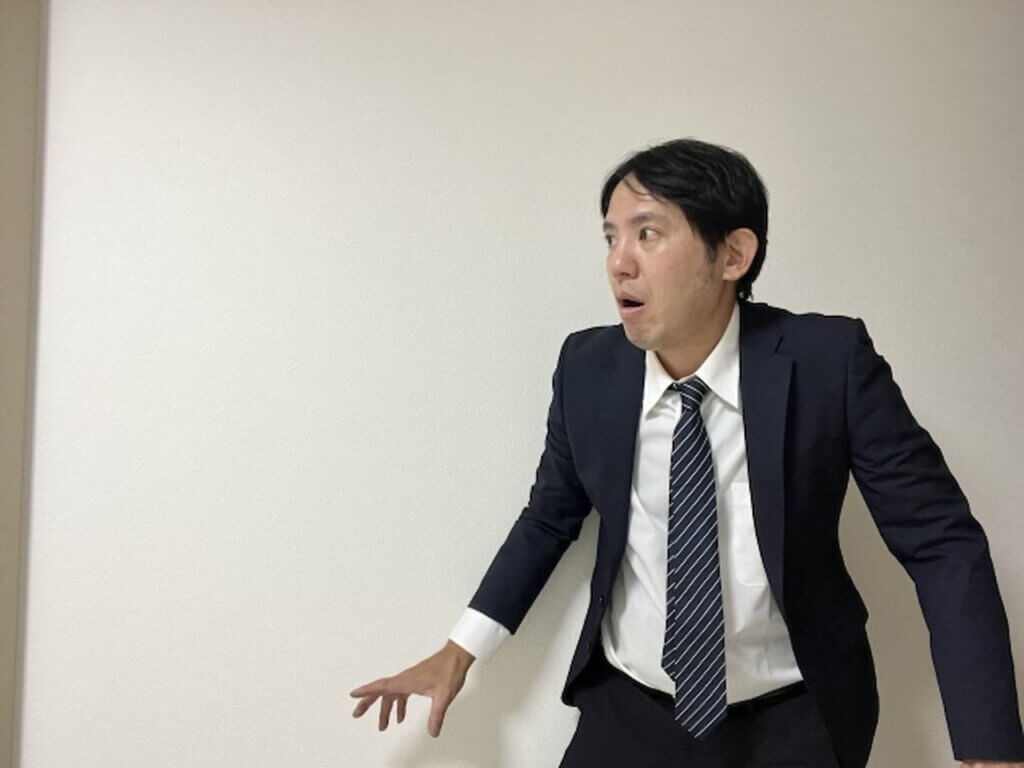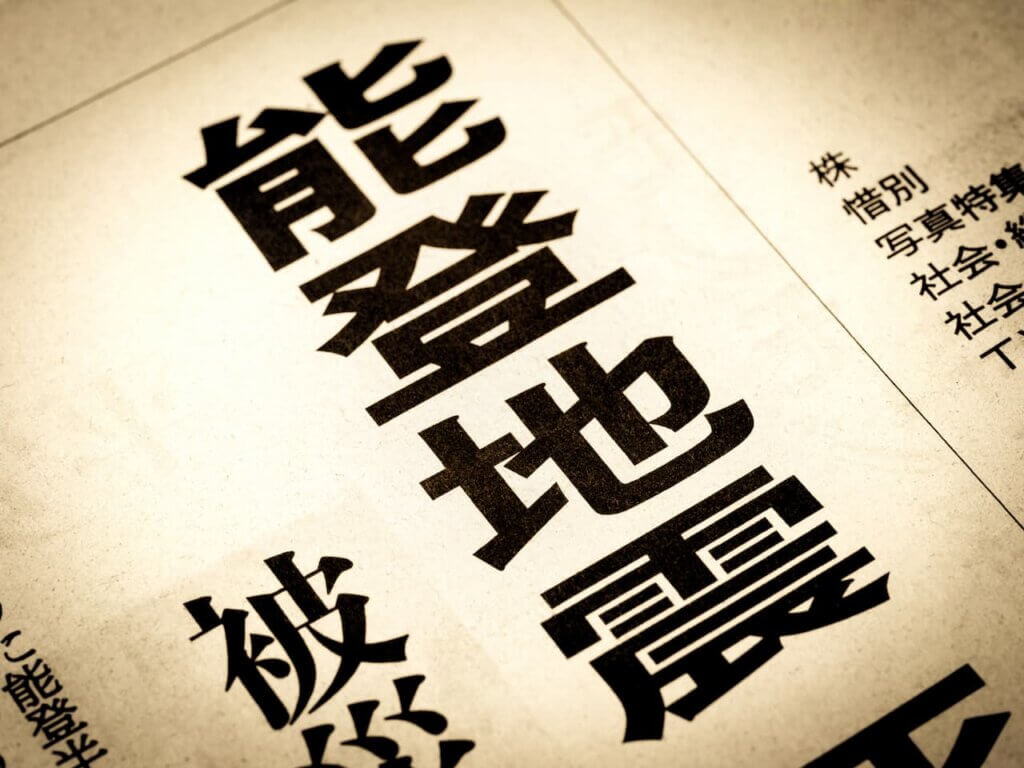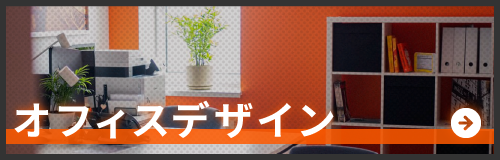オフィスで地震が起きたらどうすればいいのか、不安に感じる人は多いと思います。自然災害の多い日本では、大規模な地震がいつ起きてもおかしくありません。地震から従業員を守り、被害を最小限にとどめるためにも準備はしておきたいですよね。そこで、企業が行うべき地震対策5つと、オフィス家具やパーテーションの転倒を防ぐ方法を詳しく解説します。
オフィスの地震対策が必要なワケ
オフィスでも地震対策をやるべき4つのワケを解説します。
従業員を守るため
企業は安全なオフィス環境を整えて、従業員を守る責任を持ちます。「安全配慮義務」と言われる労働契約法に基づく法的な義務です。オフィス家具が簡単に倒れたり、ガラスが割れたりすると、従業員が負傷してしまうかもしれません。
企業活動を継続させるため
地震によるオフィスの損壊や通信障害、停電などが起きても、企業活動の継続を目指す必要があります。もちろん、一時的な停止はやむを得ない場合も多いでしょう。しかし、長期的な停止は取引先や顧客を不安にさせたり、資金繰りを悪化させたりする恐れがあります。
財産や設備を守るため
企業は、従業員はもちろん、財産や設備も守らなければなりません。大規模な地震が起きると、建物が倒壊したり、オフィスの家具や内装、情報機器などが損壊したりするリスクがあります。
大規模地震の切迫性が高まっているため
日本は自然災害が多く、なかでも大規模な地震の切迫性が高まっていると言われています。とくに発生確率が高いものとして「南海トラフ地震」や「首都直下地震」の2つがニュースでもよく取り上げられています。
オフィスの地震対策のポイント5つ
地震に備えて企業が行うべき対策5つを解説します。実践して安心できるオフィスを目指しましょう。
オフィス家具やパーテーションの固定
重いキャビネットや背の高いパーテーションなどは、壁や床に固定して転倒を防止して下さい。以前、筆者はオフィス家具メーカーに勤務していました。皆さんはキャビネットが想像以上に重いことをご存知ですか。
オフィスの家具はスチールなどで頑丈に作られているため、倒れると大けがに繋がります。また、避難経路を塞いでしまう恐れもあるためしっかり固定しておきましょう。
避難経路の整頓
オフィスの避難経路や通路は整頓し、いつでも利用できる状態にしておきましょう。とくに、非常時はエントランスや非常口付近に人が集中しやすくなります。不用品や書類などで通路を塞がないようにして下さい。
レイアウトには建築基準法と消防法が関係します。しかし、オフィス内の通路幅はどちらにも定められていません。一般的には、建築基準法施行令によって一定規模の学校や病院等に定められている「廊下の幅」を、オフィスでも参考にしています。
<廊下の幅>
- 片側に居室がある通路:1.2m以上
- 両側に居室がある通路:1.6m以上
避難用品の備蓄
非常用の備蓄を準備し、オフィス内の分かりやすい場所に保管します。いざという時に取り出しやすいことが重要です。内閣府が作った帰宅困難者対策のガイドラインでは、地震後は混乱を避けるために一斉に帰宅せず、オフィスや施設に一時待機することを基本としています。
- 飲料水
- 非常食
- ヘルメット
- 軍手
- 救急セット
- 簡易トイレ
- 懐中電灯
- モバイルバッテリーまたは電池式充電器+電池
- カイロ
- 毛布またはアルミブランケット
- ウェットティッシュ
- タオル
- ラジオまたはテレビ
情報伝達の仕組みを整える
情報伝達の仕組みを整え、地震の際に従業員と迅速に情報を共有できるようにしておきましょう。支店が複数ある場合や外出が多い企業には、安否確認サービスがおすすめです。
東日本大震災の際も、従業員の安否確認がスムーズでした。訓練機能が付いていて、普段からログインや回答の練習をしていたことが功を奏したのだと思います。また、現在ではメールだけでなくLINEなども利用可能となり、利便性がアップしています。
パソコン類やデータの保護
企業活動に欠かせないパソコンやデータも保護が必要です。例えばパソコンやサーバーは、落下防止策として耐震マットの利用やベルト固定などの方法が選べます。使っていない機器類は扉付きの収納に入れましょう。また、データはバックアップをとって遠隔地でも保管しておく方法やクラウド化が有効です。
オフィスでもデータをクラウド化しておけば消失リスクを軽減できます。また、オフィスに行かなくてもアクセスできることが役立つでしょう。
オフィス家具に対策すべき転倒防止方法
オフィス家具は様々な方法の転倒防止策があります。家具別に解説しますのでぜひ参考にして下さい。
キャビネット
オフィスキャビネットは主に次の3種類に分かれています。それぞれの特徴と地震対策向きのタイプを解説します。
オープンタイプ
キャビネットの中身が見やすく、もっとも安価なことが魅力です。しかし、地震の際にファイルなどが飛び出してしまう可能性があります。デスク付近や席の後ろに置くと、書類や物が落ちてくるリスクがあるため離して設置しましょう。
扉付きタイプ
扉の種類は、両開き・引き戸・ガラス戸などから選べます。地震で揺れても中身が飛び出しにくいため、扉付きは地震対策に向いています。とくに上段におすすめです。キャビネットの扉や引き出しには、一般的にラッチ機構という勝手に開かないためのロックが付いています。開ける際は、取っ手の内側のレバーを引くと簡単に解除できます。
引き出しタイプ
ロックができるため引き出しも地震対策向きです。ラテラルやトレーなどの種類があります。ラテラルは書類やファイルを横に並べて上から一覧できます。また、トレーはプラスチック製の透明な引き出しで、文房具の収納やレターケース等に活用されています。
キャビネットの転倒防止法まとめ
地震によるキャビネットの転倒防止方法を表にまとめました。ぜひ参考にして下さい。
| オフィスキャビネットの転倒防止法 | |||
| 種類 | 具体的な方法 | メリット・効果 | |
| 固定方法 | 壁固定 | キャビネットをL字金具等で壁に固定 | 壁沿いのキャビネットの転倒リスクを軽減 |
| 床固定 | キャビネット(ベース)を床に固定 | 転倒や移動リスクを軽減 | |
| 横連結 | 横に並べたキャビネットを連結固定 | 床面積と自重が大きくなり転倒しにくくなる | |
| 上下連結 | 上下に重ねたキャビネットを連結固定 | 上段がずれることや落下、転倒リスクを軽減 | |
| 背面固定 | 背中合わせのキャビネット同士を固定 | 床面積と自重が大きくなり転倒しにくくなる | |
| 突っ張り棒 | 天井とキャビネットを突っ張り棒で固定 | 工事不要で手軽 | |
| 設置場所 | ハイキャビネット(約2m) | ・壁沿い |
負傷リスク軽減 |
| ・執務空間から離れた収納スペース | 人から離すことで負傷リスクを軽減 | ||
| ローキャビネット(約1m) | ・執務スペース内で背中合わせに連結 |
床面積と自重を大きくして移動リスクを軽減 | |
| ・壁沿い | 負傷リスク軽減 | ||
| 選び方 | 棚タイプ | ・扉付き・ラッチ機構付きを選ぶ | 書類や機器が飛び出さない |
| 引き出しタイプ | ・ロック・ラッチ機構付きを選ぶ | 引き出しが飛び出さない | |
| 収納方法 | 重い物はなるべく下段に収納 |
下の方を重くして安定感アップ | |
| 背の高いキャビネットの上に荷物を載せない | 落下防止。怪我や避難経路を塞ぐことを防ぐ | ||
パーテーション
天井までのハイパーテーションは、床や天井などにレールを取り付けて固定します。ガラスパーテーションの場合は、飛散防止用のフィルムを張ったり強化ガラスを選んだりすることで、ガラスが飛び散るリスクを軽減できます。
一方ローパーテーションは、倒れにくいレイアウトに組み立てます。例えば、H字型やロの字型、T字型などが適しています。安定脚の使用や壁・床への固定によっても転倒リスクを軽減できます。
≫ 組立式のローパーテーション【オフィス家具通販ファニチャー】
キャスター付き家具
キャスターが付いているオフィス家具は、例えば、衝立やパネル、テーブル、ホワイトボードなどです。地震の揺れで動いてしまうと、人にぶつかったり避難経路を塞いだりして危険です。通常はストッパーをかけておき、移動させたいときにその都度解除して下さい。
デスク
オフィスのデスク本体も床に固定できます。例えば、脚のアジャスター部分に金具を取り付けてアンカーボルトを打つ方法などで固定できます。また、地震の際にデスクの下にもぐれるように、足元に大きな荷物を置かないようにして下さい。平机の下にデスクワゴンを入れている場合は、通常時はストッパーをかけて動かないようにしておきましょう。
オフィスの地震対策ポイント5つと家具にやるべき転倒防止法【まとめ】
オフィスの地震対策のポイント5つと、家具にやるべき転倒防止方法を解説しました。近年、日本では大規模な地震の切迫性が高まっていると言われています。従業員の命を守り、企業活動を継続させるためにも対策は必須です。